桐生タイムス復刻記事『勝負師の慧眼 深層の思い断ち難く』
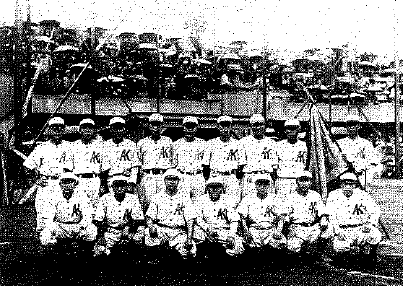
稲川東一郎は、その野球人生のなかで三度、監督として全国制覇に王手をかけている。
第十三回選抜大会、第二十七回選抜大会、そして、この第十七回都市対抗野球大会である。しかし、そのいずれも勝利の女神はほほ笑まず、悲運の闘将の名はつきまとった。
すでに語りつくされている稲川野球の情熱と実績だが、いま少しその人となりに迫ってみよう。
青木正一らOBは、よく桐中グラウンドに顔を出した。彼らが現れると「何か新しく学んだものはないか」と必ず尋ねたという。あればすぐに学生たちを指導してみらい、その話の間、じっと耳を傾けてメモをとった。
権威にこだわらぬ柔軟な姿勢は晩年まで変わらず、武蔵の『五輪の書』を座右の銘とした精神野球と両輪をなしていた。しかも部員の進路の面倒は最後まで見届け、「ほんとうに頭が下がった」と青木は話す。
戦後開いた稲川道場は、自宅の庭をつぶして建てた。さらに八畳二間を合宿所に改築、選手たちの健康管理にも力を注いだ。
栄養面は元子夫人、健康面は山田嵓が面倒をみた。選手たちは見違えるような体力をつけたのである。
その道場が、選抜の活躍によって全国の知るところとなり、見学希望者が相次いだ。時の文相天野貞祐は、質素な道場の造りに感激し、後に「これが高校野球の原点だ」と『蛍雪時代』の巻頭に書いた。
「稲川に野球を学びたい」という沖縄の指導者を、山田が案内したことがある。折しもお盆、合宿所は閑散としていた。
その洗濯場で、選手のユニホームを黙々と洗う稲川の姿を見て「野球を教わる必要がなくなりました。桐生の野球は強いわけです」と、感慨深そうに帰っていったという。
そうした厳しさ、温かさをほうふつさせる稲川像から、むろん勝負へのこだわりは見えてくる。しかし、そのこだわりとは、あくまでゲームセットまでの話だ。
優勝旗を逸したこの試合をスタンドから観戦していた新井総一郎(72)。桐中時代は部員ではなかったが、野球仲間とウマが合い、稲川ともよく酒を飲んだ。
向こう意気の強さはヤクザも裸足、野球を愛し、目は子供のように澄んでいた稲川である。そんな人柄を慕う新井が、仕事の悩みを相談したことがあった。
稲川は迷いを見抜いて「やりたいのか、やりたくないのか」と言う。やりたいと答えると「ならやればいい。失敗してもいいんだよ、それで」と言ったそうである。
試合に敗れても、車中でペンを走らせながら、次を次をと考える思考の持ち主であることは、多くの人が証言をするところだ。その稲川が、黒獅子旗には、断ち難い未練を見せた。なぜだろう。
世の中には、時代のにおいを鋭敏にかぎとることのできる人がいるものである。稲川もまたそうであったという保証はないが、全桐生が背負って生まれた時代的役割というものを、老練な勝負師の慧眼(けいがん)はとらえていたはずである。
桐生という一地方都市に忽然(こつぜん)と現れたクラブチームが、全国の強豪を向こうに回して一歩も引かずに戦い、優勝することが、戦争で疲弊した世の中にどんな希望をもたらすか、野球を肌身に染み込ませてきた稲川にとって、それは理屈ではない。
さらにもう一つ、手塩にかけ、完成されて戻ってきた選手たちをとどめておける時間がさほど長くないことも、指揮官の本能は感じとっていた。
つまり、稲川の心に「次」は描けなかったのである。この日この年だからこそ、大日本土木のような企業チームではなく、市民パワーの草の根集団「全桐生」が勝つことに強烈な意味があった。
試合に負けた悔しさよりも、そんな深層のシミュレーションが、おそらく断ち切れなかったのだ。(青木修記者)
資料協力:桐生タイムス
