桐生タイムス復刻記事「延長の王者 次々と強豪なぎ倒す」
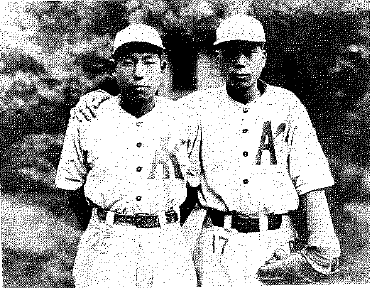
敗戦から一年を経ても、大空襲の傷あとがいまだ生々しい東京であった。夏の直射と排煙にむせながら、全桐生の選手たちが到着したのは日本橋の一軒家である。
旅館を確保できず、困り切っていたところに、後援者が提供を申し出てくれた。
渡りに舟の、ありがたい好意であった。全員が何とか宿泊できる広さがあり、炊事や洗濯の賄いは、稲川元子監督夫人ほか、地元から二人の応援を得ることができた。
大会に臨む男たちに先んじて、彼女たちの活躍は実に華々しかったという。
第十七回都市対抗野球大会の開幕は1946年(昭和21年)八月三日である。全国から、この後楽園に参集した獅子たちは全部で十六チーム。
神戸、川崎、海南、福島、岐阜、広島、富山、東京、八幡、横浜、桐生、大阪、徳島、京都、函館、名古屋。
いずれも強豪ぞろいだが、そのほとんどは一流選手をかき集めた企業が太いシンとなっており、一地方都市の出身者でまとめたクラブチーム全桐生は、明らかに異色であった。
優勝候補は、神戸、大阪、名古屋、八幡など。下馬評は、桐生の名前をかすめてもいない。さて、いよいよ本番である。
中等野球、あるいは大学、社会人、プロと、戦前活躍していた男たちが顔をそろえたのだ。開会式直前の舞台裏は、さながら同窓会のようになった。
再び野球で会えた喜びは、何物にもかえがたかったのである。やがて、笑顔をグッと引き締めて、超満員の観衆が見守るグラウンドへと、各チームは歩き出した。
ユニホームについた真新しい緑の「AK」。全桐生は胸を張って球場の土を踏んだ。
大会三日目の五日、全桐生、満を持しての登場である。スタンドには大勢、桐生のファンが詰めかけていた。午前十時の試合開始に間に合わせようと、前日の夜、市役所の前をトラックで出発した一行と、列車組である。
緒戦の相手は古豪浪商OBが並ぶ全大阪。対する全桐生は中村以下、三輪、皆川、大塚、青木、稲川、池田、木暮、常見の先発オーダーだ。ベンチでさい配をふるうのは、もちろんご存じ稲川東一郎。
試合は三回表、全大阪が2点を先行した。予選から、つねに圧倒的優位で試合を進めてきた全桐生にとって、初めて後手に回る展開である。
だが、ここに覚せいした脅威の粘り腰が、この大会の球趣をことのほか盛り上げていくことになった。
延長十回裏、全桐生は3-2のサヨナラ勝ちで全大阪を下すと、続く二回戦では八幡を延長十回4-3のサヨナラ勝ちを収め、あれよと言う間に、決勝進出を果たしてしまったのである。
その戦いぶりは、いつしか後楽園のファンから「延長の王者」の名をいただく。地元桐生はもちろん、全国のファンも熱い思いで耳目をそばだてた。
一方、広島、東鉄、神戸を下して勝ち残ってきたのは、六大学選手をずらりそろえた岐阜・大日本土木である。
桐生も岐阜も、ともに初出場同士、両雄はいったいどんな戦いを繰り広げるのか、黒獅子旗の行方をこの目で確かめようと、八月九日の決勝戦、後楽園球場は、超満員のファンでふくれあがっていた。
焼けつくような炎天下、スタンドは白一色だ。
思えば戦後すぐ、全桐生は立ち上がった。稲川のもと、野球ができる喜びを知る者たちが集い、そして、思いが一つになった。
熱狂的な球都の声援に押され、プロを破り、県を一蹴し、関東をねじ伏せた快進撃は、ふと気づいてみれば、いまや黒獅子旗の山頂が目前に迫っている。一年前、この結果をだれが想像し得ただろうか。
先行岐阜。グラウンドに散るAKの背に、稲川は「勝つ」ときっぱり声をかけた。それを飲み込む大歓声。決勝戦は始まった。(青木修記者)
資料協力:桐生タイムス
