桐生タイムス復刻記事「プロ東軍を下す 興奮に脈打つ野球場」
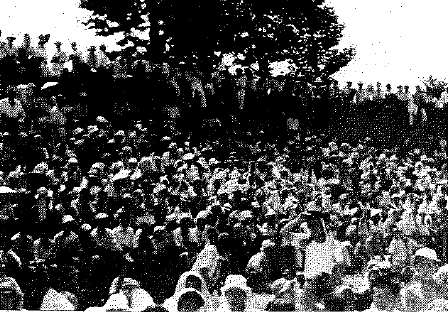
「人がこぼれる」と、青木正一は表現した。昔の野球場が、収容能力を超えた人員を抱き込んでしまったとき、試合のヤマ場で必ずといっていいほど、この現象は起きたそうである。
桐中が準優勝を飾った第十三回選抜大会(昭和11年)の決勝戦がそうだった。身を乗り出す観衆の興奮が、甲子園のスタンド後列から、大波のように前へ向かって押し寄せてくる。
その圧力のため最前列はスタンド内にとどまることができなくなって、フェンスを超え、グラウンドにこぼれ出してしまうのだ。
11月17日の野球大会初日、新川球場の熱気のほとばしりはまさにそれで、フェンスのない外野など、すでにファンが芝生にあふれ出している。
観衆一万、それは有料入場者であり、球場外側の高木によじ登った人、ぐるり取り巻くファンも加えれば、まずそんな数で収まりそうにない。
この野球大会は、17日から12月1日までの合計7日間、9試合が予定されていた。 ファンのお目当てはむろん全桐生のデビューである。 何しろ、戦争で休眠していたプロ野球団が、再出発をかけて参加している。
相手はいずれも強豪ぞろいなのだ。まずは東京セネタース対全桐生、そして、現在のオールスター戦に相当する全日本職業野球団東西対抗戦。
さらには、その盛り上がりを受けた形で全日本と全桐生が対戦する。顔見せ興業としては、まさに最高の舞台が用意されていたのである。
セネタースの戦いは、二試合とも全桐生が敗れたが、期待に違わぬ接戦で観衆は大喜びだった。大下、飯島、長持、白井といった当時の有力メンバーと、がっちり四つに組んだ。
その試合の審判を務めたのは金井吉雄(西中校長)の父裕一と、河合、馬場ら地元の審判員たちである。「おれはプロの試合のジャッジをやった」。それは 裕一の自慢のひとつだった。
市役所で配給の仕事に携わっていた裕一は、稲川東一郎ら関係者から、全桐生のユニホームの調も頼まれていた。
「灰色とえんじのだんだらストッキング、それしかなかったらしく、ユニホームもやっと間に合ったようです」。
その父親の晴れ姿を、金井はスタンドから眺めたが、全桐生の選手の勇姿にも一目であこがれた。ユニホームの胸に、まだあの「AK」のデザイン文字はなかった。
球場は連日大入りである。明日のことが分からず、今日を生きるのが精いっぱい。そんな戦後の混乱の中で、この一角だけは際立っていた。
駐在軍の兵士たちがあの青年たちの顔に見た、あふれるような笑いと活気が、いまは球場全体を巻き込んでいるのである。
25日午後、待ちに待ったプレーボールだ。西軍が日程の都合で早めに帰ったため、事実上は東軍との対戦となったが、彼らを相手に、わが全桐生がどんな戦いを挑むのか、観衆の目は当然、一挙一動に注がれていた。
その期待にこたえるように、全桐生は四回までに3点を先行。それからは、追いつ追われつ、はらはらどきどき、息もつかせぬ展開である。
九回、同点に追いつかれた段階で一度はため息に変わった観衆の声が、再びうねり出したのは延長12回、貴重な1点を挙げた全桐生は、これを見事に守り切り、東軍を下してしまったのだ。
興奮爆発、球場は脈うった。逆に、青ざめたのは東軍の監督、藤本英雄(巨人)である。「プロがノンプロに負けたのでは、とんだ恥さらしだ。この結果は、新聞にはのせんでくれ」。試合後、渋い顔で球場をあとにした。
当時の新聞をひもとくと、東軍の名が「オール東京」というノンプロに化けている。武士の情けであった。スコアは8-7。こうして、ひとつの伝説が生まれた。(青木修記者)
資料協力:桐生タイムス
