桐生タイムス復刻記事『無念の敗戦「東ちゃん」、荒れる』
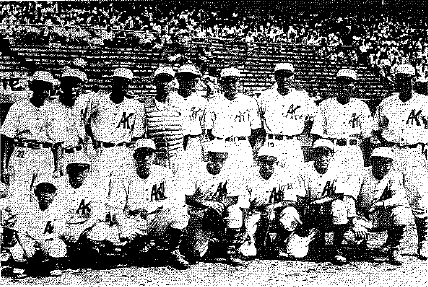
全桐生の木暮英路は、ここまでの三試合いずれも先発に起用されている。
疲労感は覆うべくもないが、名古屋戦を二回から救援した三輪裕章に安定感がある。木暮でいけるとこまで行く。それが稲川の作戦であった。
その木暮が四回表、三連続四死球で無死満塁のピンチを招き、三輪にスイッチした。そこまでは予定の行動だったが、鉄壁の内野に手痛いエラーがでた。
そこでまず2点、動揺に乗じ、岐阜はすかさずスクイズで加点した。以降の岐阜は鳴かず飛ばず、これがただ一度のチャンスだったのである。
これに対し、二回、四回、六回、八回と無死の好機をつかみながら全桐生には決定打がでない。
岐阜の先発は、ソ連抑留から帰ったばかりの中原宏である。ストライクともボールともつかぬ球が、どうしてもとらえきれないのだ。
「じつにしらばっくれたボールだった」と、青木正一はあのときの緩急をつけた中原の投球術を思い起こす。一度のチャンスをものにした岐阜と、再三の好機をつぶした桐生。
形の上では確かにその通りだが、そのクセ球に惑わされた分、「伯仲とは言えず、四分六でしたね」と振り返る。
午後三時の開始から一時間五十四分。後楽園の日はまだ高く、戦う気力はなお燃え盛るなかで九回の裏は閉じた。
3-0。この大会で初めて体験する九回試合。「延長に持ち込めば」の夢は潰え、煙に巻かれたナインの目前で、黒獅子旗は岐阜の手に帰した。
その落胆が、どれほどのものであったかは、当の選手たちでなければわかるまい。悔しさを胸に圧しこらえ、閉会式に臨む足取りは重かった。
ウイニングボールが岐阜の手に落ちた瞬間から、一緒に走り続けてきた日々の感慨が一気に押し寄せてきた応援団。むろん、その健闘を万雷の拍手でたたえることを忘れなかった。
が、このときの表彰風景の異形を、後々まで脳裏に刻んだ人びともいる。
ベンチの裏から表彰式のグラウンドへ、黒獅子旗につかみかかるかのような東ちゃんの姿が見えたのである。それを、しきりにとめようとする人たちがいた。
何があったのだろう。この模様を、グラウンドにいた青木はこう証言する。「閉会式で整列し、あいさつしてるのに、そばで万歳をやってしまったんです」。
稲川は酔っていた。猛烈な暑さとこう着した試合展開にのどが渇き、水筒に口をつけた。だれの仕業か、入っていたのが酒、根が好きな人だから、思わずぐっと、飲み込んでしまったのだ。
気をきかせたのは、チーム関係者のような顔でベンチに腰を降ろす桐中名誉応援団長、吉野錦風であった。ふだんの稲川が試合中に水を含むことはない。
吉野はそれを承知の上で、優勝祝いに振る舞おうと、こっそり持ち込んでいたのである。いったいどこで手に入れたのか、当時出回っていたヤミ焼酎は、まわりが早かった。
困ったのは選手たちだ。青木の諫めに稲川は黙った。だが今度は帰り際、岐阜の選手をみつけ、コンチクショウと石を投げるまねをした姿を、中村はみた。
もともと熱血漢である。でも、ユニホームを着た稲川がおよそ見せたことがない破天荒の連続に、真面目な中村は「おれたちが、だらしなかったからだ」と、申し訳なさでいっぱいになったという。
酒のことはすでに時効、稲川と吉野という無二の間柄をしのばせる逸話に昇華させたい。
だが、はからずも出た稲川のあらわな黒獅子旗へのこだわりは、単に酒の勢いでは説明がつかない。言葉ではなく、体で表現してみせたかった気持ちがあったはずである。いったい何だろうか。
それをたどる道筋に、全桐生という奇跡のチームの本当の姿が、見えてくるような気がした。(青木修記者)
資料協力:桐生タイムス



